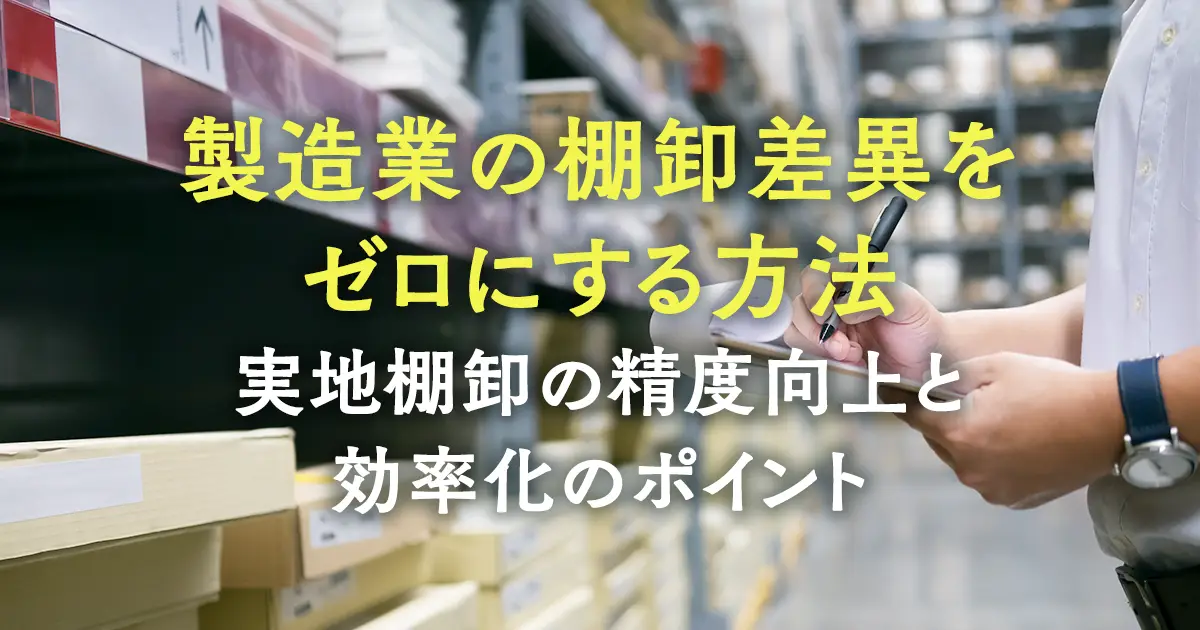きし
きしこんにちは。製造業の会計・税務に強い、栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。
「棚卸の時期になると、いつも帳簿と実際の在庫が合わなくて困っている」
「毎年棚卸差異が出てしまって、原因がよくわからない」
そんなご相談を、私たちマロニエ会計事務所では本当によくお受けします。
実際に私がお客様とお話ししていると、多くの製造業の経営者の方が「棚卸は面倒な年末作業」と捉えていらっしゃることがわかります。
 きし
きしでも、これは大きな誤解とも言えるのです。
棚卸差異というのは、単なる数字の不一致ではありません。
私の経験では、棚卸差異が大きく出る会社は、日々の業務プロセスに何らかの問題を抱えているケースがほとんどです。
そして、この差異を放置してしまうと、不正確な利益計算につながるだけでなく、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を招いてしまいます。
私がこれまで見てきた製造業のお客様の中でも、棚卸差異をゼロに近づけることができた会社は、確実に経営が安定し、資金繰りも改善されています。
この記事を読んでいただければ、棚卸業務を単なるコストのかかる作業から、経営の健全性を示すバロメーター、そして競争力を高めるための戦略的ツールへと変えていく第一歩が踏み出せるはずです。
マロニエ会計事務所では、製造業に特化した税務・会計サービスをご提供しています。
棚卸差異が製造業経営に与える影響とは
私がこれまで製造業のお客様の財務を見てきた中で、「たかが棚卸差異」と軽く考えている経営者の方が意外に多いことに驚かされます。しかし実際には、棚卸差異は経営の根幹を揺るがす重大な問題です。
特に製造業では、原材料から仕掛品、完成品まで多様な在庫を抱えているため、差異が発生すると影響が広範囲に及びます。
棚卸精度が経営に与える具体的影響
棚卸精度が経営に与える具体的な影響としては以下の3つが挙げられます。
- 財務面での影響
- 業務面での影響
- 顧客への影響
それぞれ私がお客様によくお話しする具体例をご紹介いたします。
財務面での影響では、まず利益計算の精度が大きく狂ってしまいます。在庫は売上原価の計算に直接影響するため、棚卸差異が1円あれば、利益も1円ずれます。私が実際に見た事例では、月次で500万円の差異が発生し、その月の利益が大幅にマイナスになってしまったケースもありました。
業務面での影響も深刻です。帳簿上は在庫があるのに実際にはないという「欠品」が発生すると、お客様への納期遅延につながります。逆に、実際には在庫があるのに帳簿上はないと「過剰発注」をしてしまい、キャッシュフローを圧迫します。
 きし
きし私のお客様でも、「月末になって急に在庫が足りないことがわかって、大慌てで緊急発注した」という経験をお持ちの方が非常に多いです。
顧客への影響も見逃せません。納期遅延や品質不安定は、長年築き上げてきた顧客との信頼関係を一瞬で壊してしまう可能性があります。
信用は足し算ではなく掛け算というのはよく言われることです。
棚卸差異ゼロを目指すことのメリット:連鎖する好循環
棚卸差異をなくす努力は、単なるコスト削減活動ではありません。それは、企業全体のパフォーマンスを向上させるための取り組みになります。
私がこれまで支援してきたお客様で、棚卸差異ゼロの状態を達成された企業では、以下のような経営上のメリットを実感していただいています。
キャッシュフローの最適化: 正確な在庫レベルを維持することで、不要な在庫に資本が固定化されるのを防ぎ、企業のキャッシュフローと資金繰りを大幅に改善できます。
業務効率の最大化: 信頼性の高いデータに基づき、適切な発注、効率的な生産計画、そして紛失在庫の捜索や緊急棚卸といった非生産的な作業に費やされる人件費の削減が可能になります。
信頼性やコンプライアンスの向上: 正確な在庫システムは、社内外からの信頼の礎となります。会計監査や税務調査、金融機関からの融資審査などをスムーズに進めるだけでなく、より高度な経営戦略の導入を可能にします。
財務報告における在庫の役割
在庫がなぜこれほど重要なのかを理解するために、私がお客様によくお話しするのが、在庫の会計上の役割です。
企業の利益は、以下の計算式によって算出されます。
まず、売上原価は次のように計算されます。
売上原価 = 期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高
そして、この売上原価を用いて、企業の売上総利益(粗利益)が確定します。
売上総利益 = 売上高 − 売上原価
この2つの式から明らかなように、「期末棚卸高」の金額に1円の誤差があれば、それはそのまま「売上原価」に1円の誤差を生み、最終的に「売上総利益」に1円の誤差をもたらしてしまいます。
つまり、棚卸の精度は、企業の損益計算そのものの信頼性を決定づけることになります。
実地棚卸の精度を上げる具体的な方法
実地棚卸というのは、実際に倉庫や店舗にある在庫を目で見て手で数える作業です。その成功は、当日の作業内容よりも、事前の準備によってほぼ決まると言っても過言ではありません。
ここでは、私たちがお客様にお伝えしている、伝統的な一斉棚卸を最高精度で実施するための方法をご紹介していきます。
実地棚卸の事前準備のポイント
棚卸の精度は、計画段階でほぼ決まってしまうと言っても過言ではありません。行き当たりばったりの作業は、混乱と不正確な結果を招くだけと言えます。
棚卸計画書の策定: これは棚卸全体の設計図になります。明確なタイムスケジュール、棚卸対象エリアを網羅した倉庫見取図、そして誰が読んでも同じ作業ができる詳細な棚卸マニュアルの3点は不可欠です。
私がお客様によく申し上げるのは、特に重要なのが棚卸中の在庫の動きを完全に停止させるための「カットオフ」手続きです。棚卸期間中の商品の入出庫を厳密に管理するルールを定め、全関係者に徹底していただく必要があります。
チーム編成と役割分担: ミスと不正を防止する基本は「2人1組(ツーマンセル)」での作業です。
1人が実際に数を数える「計数者」、もう1人がその数値を棚卸票に記録する「記入者」となります。
そして、各チームの進捗を管理し、不明点の判断や棚卸票の回収・配布を行う「責任者」を必ず任命していただきます。この体制により、リアルタイムでのダブルチェック機能が組み込まれます。
倉庫の事前整備(5S活動): 雑然とした倉庫での正確な棚卸は不可能です。
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底が不可欠になります。
- 整理: 在庫以外の私物、ゴミ、不要な資材を完全に撤去します。
- 整頓: 同じ品目は同じ場所に集約します。通路、棚、箱ごとに明確なロケーション番号や品目ラベルを貼り、誰が見ても何がどこにあるか分かる状態を作ります。
- 清掃: 清潔な環境は、作業の安全性と従業員の士気を高めます。
- 清潔: ラベルの形式や掲示方法などを標準化し、常に維持します。
- 躾: これらの状態を、棚卸の時だけの一時的なものではなく、日常の標準業務として定着させます。
特殊在庫の隔離: 棚卸作業を開始する前に、特別な扱いが必要な在庫を物理的に別の場所へ移動させ、明確に区分けしておく必要があります。
これには、顧客からの預かり品(預かり在庫)、委託販売先にある在庫(預け在庫)、そして破損品や長期滞留品(不良品)などが含まれます。これらを明確に区別しないと、誤って自社の資産としてカウントしてしまい、重大な会計上の誤りに繋がってしまいます。
経理部による棚卸説明会の実施:棚卸の際の留意点を経理部が現場担当者に向けて説明する場を設けることも有効です。実際に私が勤務していた工場では、実地棚卸の時期には合計3~4回ほどの実地棚卸説明会の時間を設け、工場の全ての人が参加するように呼び掛けていました。
効率的な棚卸作業の進め方
準備が整ったら、計画に沿ってカウント作業を開始していきます。
カウント手法:タグ方式 vs. リスト方式
タグ方式: 非常に精度が高い反面、時間がかかる手法です。
計数者は、カウントした在庫のロットごとに、連番管理された「棚札(タグ)」を貼り付けていきます。倉庫全体の在庫にタグが貼り付けられた後、そのタグをすべて回収します。
タグの連番をチェックすることで、カウント漏れのエリアがないかを確認できます。
物理的な札を使うため、二重カウントやカウント漏れが起こりにくいのが最大の利点です。
リスト方式: 比較的短時間で作業できますが、エラーが発生しやすい手法です。
事前に在庫管理システムなどから出力した在庫リストを元に、実際の在庫数を確認し、実数をリストに記入していきます。
この方法の弱点は、リストに載っていない商品(計上漏れ)を見逃す可能性があることと、リストに記載された数量に引きずられてしまい、思い込みでカウントしてしまうバイアスがかかりやすいことです。
リスト方式は、日頃から在庫管理システムの精度がある程度高い企業でなければ採用は困難でしょう。
精度の確保
体系的なカウント経路: カウント漏れや重複を防ぐため、一貫した作業経路を義務付けます。
例えば、「棚の上段から下段へ、左から右へ」といったルールを定め、通路を蛇行するように(逆Sの字)進むことで、エリア全体を網羅的に確認できます。
ダブルチェックの徹底: 一つのエリアのカウントが終了したら、計数者と記入者が役割を交代して再カウントを行うか、別の監査チームが抜き打ちで検算(スポットチェック)を行います。
これは、ミスをその場で発見するための非常に重要な内部統制です。
棚卸後の差異分析と改善方法
カウント作業の完了は、棚卸の終わりではありません。ここからの集計と分析こそが、次の改善につながる重要なプロセスです。
データ集計: 使用したすべての棚卸票を回収し、未使用や書き損じ分も含めて、配布した枚数と一致するかを確認します。これにより、棚卸票の紛失がないことを保証できます。その後、データを集計していきます。
比較と差異の特定: 集計された実地棚卸高(実際の在庫数量)を、帳簿棚卸高(あるべき在庫数量)と比較します。この差が「棚卸差異」になります。
差異原因の調査: 重大な差異が発見された場合、安易に帳簿を修正してはいけません。直ちに原因調査に着手していただきます。対象品目の再カウント、最近の入出庫伝票の確認、データ入力ミスのチェックなど、考えられる原因を一つずつ潰していきます。
目的は、単に数字を合わせることではなく、なぜ差異が発生したのかという「根本原因」を突き止めることです。
最終確定: 徹底的な調査を経てもなお原因が不明な場合に限り、最終的に帳簿上の在庫数を、確認済みの実在庫数に合わせる修正を行います。この会計処理によって、「棚卸減耗損」または「棚卸差益」が計上されます。差異を会計数値にまで反映して初めて、棚卸が確定したといえます。
年一回の実地棚卸は、単なる会計手続きではありません。それは、企業の日常的な業務精度を映し出す「健康診断」です。
大きな差異が出るということは、日々の入庫検品、出庫管理、データ入力、保管方法といったプロセスに何らかの「病気」が潜んでいる証拠です。
 きし
きししたがって、実地棚卸は差異を解決する「治療法」ではなく、問題の根本原因を特定するための「診断ツール」として活用すべきだと私は考えています。
一斉棚卸 vs 循環棚卸|どちらを選ぶべきか
棚卸の「方法」を理解した次に考えるべきは、それを「いつ」「どのように」実施するかという戦略です。
企業の状況に応じて、最適なアプローチは異なります。ここでは、二つの主要な棚卸のアプローチを比較検討していきます。
一斉棚卸(定期的棚卸)とは
一斉棚卸(定期的棚卸)とは、決算日や半期末など、特定の基準日において、全在庫を一度にまとめてカウントする伝統的な手法です。
一斉棚卸(定期的棚卸)を行うには、正確な在庫数を把握するため、カウント期間中は入出庫業務を完全に停止し、在庫が動かない状態を作り出す必要があります。
メリット: 正しく実施されれば、期末の財務諸表に反映される在庫資産額の正確性が非常に高くなります。また、問題点を一時期に集中して洗い出すことができるため、エラーの発見が比較的容易なんです。
デメリット: 業務を完全に停止させるため、事業への影響が相当大きくなります。短期間に多くの人員と時間(残業など)を投入する必要があり、コストもかさんでしまいます。さらに、数ヶ月前に発生したエラーが期末になって初めて発覚するため、その根本原因を特定することが難しくなってしまいます。
循環棚卸(サイクルカウンティング)とは
循環棚卸(サイクルカウンティング)全在庫を一度に数えるのではなく、在庫をいくつかのグループに分け、毎日や毎週といった短いサイクルで、特定の範囲の在庫を順番に継続的にカウントしていく手法です。
循環棚卸(サイクルカウンティング)を行うにあたり、通常業務を停止させる必要がありません。A
BC分析などを用いて、高価で動きの速いA品目を高頻度で、安価で動きの遅いC品目を低頻度でカウントするなど、重要度に応じた計画を立てることが一般的です。
メリット: 業務停止が不要なため、事業への影響がありません。エラーが発生してから短期間で発見されるため、原因の特定と対策が容易になり、継続的な業務改善につながります。少人数の専門チームで実施できるため、従業員の負担も少なく、年間を通じて高い在庫精度を維持できます。
デメリット: 複雑な棚卸ルールの設定と、それを支える在庫管理システムの導入が不可欠です。在庫が動いている中でカウントするため、管理が不十分だと逆にエラーを誘発する可能性もあります。また、全ての品目を一度に数えるわけではないため、会計監査人に対してそのプロセスの妥当性を明確に説明できる体制が求められます。
自社に最適な棚卸方法の選び方
どちらのアプローチが優れているかは、企業の特性によって異なります。事業規模、在庫管理単位数、在庫価額、業務の複雑性、そしてITシステムの導入状況などを総合的に勘案して決定すべきです。
なお、折衷案として、日々の業務管理と精度向上のために「循環棚卸」を導入しつつ、期末には会計監査の要求を満たすために「一斉棚卸」を補完的に実施するといったハイブリッドなアプローチをお勧めすることもあります。
また、工場ごとに「循環棚卸」と「一斉棚卸」を使い分けるようなケースもあります。
| 特徴 | 一斉棚卸 | 循環棚卸 |
| 実施頻度 | 年1~2回(定期的) | 毎日・毎週(継続的) |
| 業務への影響 | 全面的な業務停止が必要 | 業務停止は不要 |
| 作業工数 | 短期間に集中して多くの作業 | 長期間にわたり少しずつの作業 |
| エラー発見速度 | 遅い(最大1年の遅れ) | 速い(数日~数週間) |
| 根本原因分析 | 困難 | 容易 |
| 最適な用途 | 期末の財務報告、単純な業務 | 継続的な業務改善、複雑・大量の業務 |
| 主な課題 | 事業活動の中断 | ルールやシステムの設定が煩雑 |
両者はトレードオフの関係にあり、自社の最優先課題が何か(例:期末報告の絶対的な正確性か、日々の業務効率の改善か)といった点も考慮する必要があります。
製造業でよくある特殊在庫の棚卸ポイント
この章では、特殊な在庫に対する対応方法をご紹介していきます。
自社所有でない在庫の管理
棚卸において、自社の資産ではない在庫を誤って計上したり、自社の資産である在庫を計上し忘れたりすることは、頻繁に起こるエラーの一つです。
預け在庫(委託販売在庫など): 自社の商品を、顧客の拠点や外部の倉庫に預けている状態の在庫ですね。これは間違いなく自社の資産であり、棚卸の対象に含めなければなりません。
預かり在庫: 他社の所有する商品を、自社の倉庫で一時的に保管している状態の在庫です。これは自社の資産ではないため、棚卸の対象から除外しなければなりません。
「預け在庫」の管理手順: 在庫を預けている第三者(委託先など)に棚卸基準日時点での在庫証明書(預かり証)を発行してもらいます。もしその在庫の金額的重要性が高い場合は、自社の担当者や会計監査人が実際に現地を訪問し、棚卸に立ち会うこともあります。
「預かり在庫」の管理手順: これらの在庫は、自社の在庫と明確に区別できる場所に物理的に隔離し、「棚卸対象外」や「預かり品」といった表示を誰の目にも明らかなように掲示しておく必要があります。この区別が曖昧である場合には、会計監査人の実地棚卸立会で指摘事項になる可能性もあります。
不良在庫の識別と評価
特に会計監査が入っているような上場企業等においては、不良在庫について会計上の評価額を減少させる必要があり、不良在庫の区分管理も重要な論点となってきます。
不良在庫の識別: 実地棚卸の際には、担当者が破損品、期限切れ品、季節外れ品など、通常の価格で販売することが困難な在庫(不良在庫・滞留品)を識別し、良品とは別に集計する手順を組み込む必要があります。
具体的には正常品とは物理的なロケーションを分け、在庫管理システム上でも正常品とは異なるステータスに変更しておく必要があります。
輸送中在庫の棚卸ポイント
輸送中在庫とは、棚卸時点で自社には物理的に存在せず、輸送中の状態にある在庫のことです。
会社が売上の計上を出荷基準で行っていれば、会計上では棚卸資産に計上する必要はないことから棚卸の対象としなくとも問題ありません。
一方で、売上の計上を検収基準で行っているような場合は、まだ取引先の検収を受けていない状況であるため、会計上は棚卸資産として資産計上しなければならず、棚卸も行わなければなりません。輸送中在庫は棚卸が非常に漏れやすい在庫の1つです。
輸送中在庫の把握: 輸送中在庫の把握は工場の製造部門だけでは把握することが難しいことも多いです。ロジ部門や営業部門と連携し、棚卸時点で輸送中の在庫が発生する見込みはないかどうか、事前に確認をとっておくことが重要となります。
まとめ|棚卸差異ゼロを目指すための次のステップ
本記事では、棚卸差異をなくすための具体的な方法や注意事項をご紹介してきました。
最終的な目標は、完璧な棚卸を行うことそのものではありません。
この状態まで到達することができれば、社長や管理者はもはや在庫の数字に振り回されることなく、正確で信頼性の高いデータを基礎として、経営分析や生産管理活動を行うことができるようになります。
マロニエ会計事務所では、製造業に特化した税務・会計サービスをご提供しています。
私たちマロニエ会計事務所でも、製造業のお客様の棚卸差異の改善については数多くのご支援をさせていただいております。
「うちの棚卸、このままで大丈夫かな?」と感じていらっしゃる製造業の経営者の皆様、まずは自社の棚卸の方法を見直してみて、棚卸差異が少しでもなくなるように改善活動を進めていただければと思います。
 きし
きし製造業の支援を得意とする私たちが、皆様の棚卸業務の改善をお手伝いさせていただきます。
\ 24時間受付しております!/