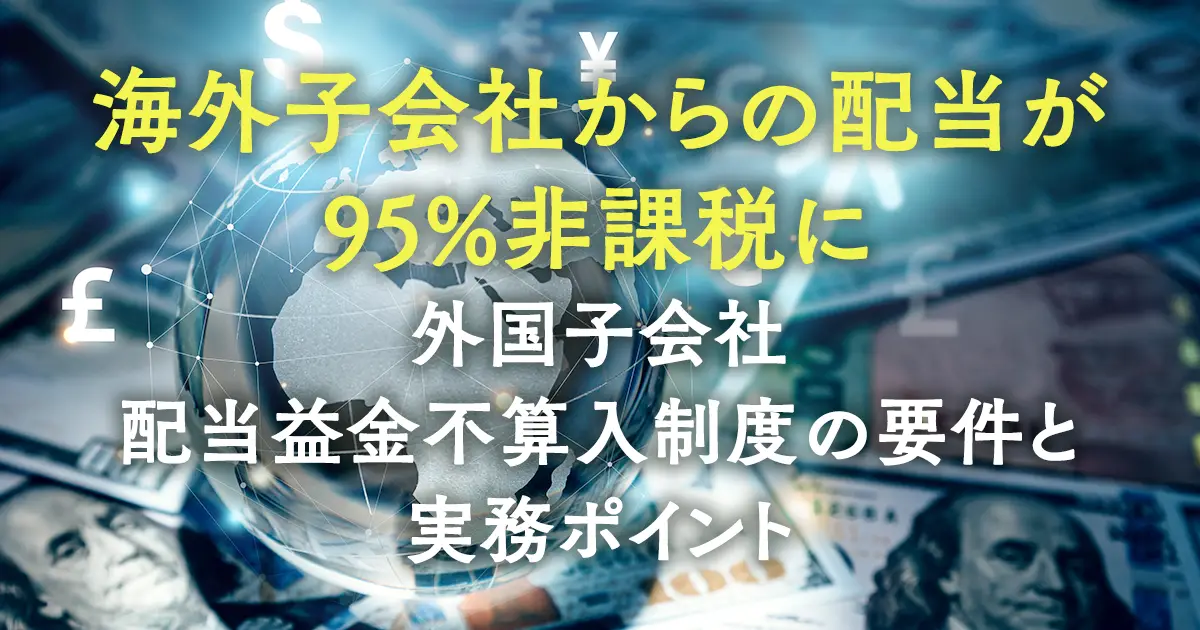きし
きしこんにちは。外国子会社配当金に強い栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。
海外進出している企業の中には、海外子会社の利益を配当で日本の親会社に還元するケースも多いと思います。
しかし、「せっかく海外で稼いだ利益なのに、日本に送金するとまた税金がかかるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この問題を解決するのが「外国子会社配当益金不算入制度」です。
通常、法人が配当を受け取った場合には利益として課税されてしまいますが、海外子会社から受け取る配当に関しては、そのほとんどを無税にできる非常に強力な節税制度があります。適用できれば配当の95%が非課税となり、企業のキャッシュフローに大きなインパクトをもたらします。
ただし、この制度を知らずに申告してしまったり、要件を満たしていないと思い込んで適用を諦めてしまったりするケースも少なくありません。
特に、株式保有割合が25%ギリギリの場合や、租税条約による特例が使える場合など、見落としやすいポイントがいくつか存在します。
そこで今回は、外国子会社配当益金不算入制度の基本的な仕組みから適用要件、さらには実務で見落としがちな会計処理上の留意点まで、税理士の視点から徹底解説していきます。
なお、本記事は令和7年4月1日時点現在の法令等に基づき記載しております。
また、記事の内容は分かりやすさのために簡略化して記載している部分があります。実際の制度の適用、検討の際には条文や顧問税理士等の意見を参考にするようにお願いいたします。
外国子会社配当益金不算入制度とは?95%が非課税になる仕組みを解説
日本の法人税法は、海外子会社からの配当を含めて全世界所得に対して課税を行います。
海外子会社が海外現地で課税された後の利益を日本親会社に配当で送金すると、原則として日本親会社でもその配当に対して課税され、国際的な二重課税が発生します。
そのため、この二重課税を排除するために、一定の要件を満たした海外子会社からの配当の95%相当額を日本で課税しないという、外国子会社配当益金不算入制度が設けられています。非常に節税メリットのある制度であり、海外子会社からの配当を受領する際は必ず検討したい制度です。
外国子会社配当益金不算入制度の適用要件|25%保有と6ヶ月継続がポイント
内国法人が、①外国子会社から受ける②剰余金の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の95%相当額が日本で課税されないかたちになります。
太字で記載した部分が重要な要件であるため、以下で解説していきます。
①外国子会社であること
外国子会社配当益金不算入制度の対象となる「外国子会社」とは、以下の要件をいずれも満たす外国法人をいいます。
要件1:内国法人のその外国法人の株式等の保有割合が25%以上であること
要件2:要件1の状態が、外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払い義務が確定する日以前6か月以上継続していること
株式等の保有割合が25%以上の状態が6か月以上継続していることが必要です。配当の直前に株式の保有割合が25%以上になるように買い増しして要件を満たすといったことはできないので注意しましょう。
租税条約に二重課税排除条項がある場合の保有割合の判定
租税条約の相手国の居住者である法人が納付する租税を日本の租税から控除する租税条約の規定(「二重課税排除条項」といいます。)には、間接外国税額控除の外国子会社の判定を行う際の外国子会社の株式等の保有割合を緩和する旨の規定が設けられていることがあります。
これは間接外国控除を適用する場合の規定なので、本来は外国子会社配当益金不算入制度には使えないのですが、法人税法施行令22条の4第7項において、二重課税排除条項で緩和された保有割合を使用しても良い旨が規定されています。
そのため、二重課税排除条項で25%未満の保有割合が定められている国に海外子会社がある場合には、保有割合の要件が緩和されることになります。
本記事執筆日現在で、主に以下のような国との間の租税条約で、25%未満の保有割合が定められています。
保有割合が25%未満だからといって諦めず、海外子会社の所在地国との間の租税条約も必ず確認するようにしましょう。
表:二重課税排除条項における株式等の保有割合
| 外国子会社の所在地国 | 株式等の保有割合 |
|---|---|
| フランス | 15% |
| アメリカ(議決権有の株式に限る)、オーストラリア、オランダ | 10% |
②剰余金の配当等の額
株式又は出資に係る剰余金(資本剰余金を除く)の配当をいいます。 また、自己株式の取得や法人清算時の出資の払い戻しに伴うみなし配当も対象になります。
配当について海外子会社で損金算入される部分がある場合
現地の税法によっては、配当金の支払いが損金算入されるようなケースもあります。
現地で配当金の支払いが損金算入される場合は、日本と海外での国際的な二重課税は生じないため、原則として外国子会社益金不算入制度の対象にはなりません。(原則法)
なお、配当の一部のみが損金算入となる場合には、その損金算入される部分だけを抽出して外国子会社益金不算入制度の対象外とし、残りの配当部分については外国子会社益金不算入制度の対象とすることもできます。(実額法)
配当の全てではなく一部のみが損金算入される場合は、実額法を使えば益金不算入制度を適用できる可能性がありますので、検討を忘れないようにしましょう。
海外子会社配当に係る外国源泉税の取扱い|控除できない理由と例外
海外子会社が配当を支払う際に現地で源泉税が発生することがあります。
通常の利子や配当ですと、現地で発生した源泉税は日本において外国税額控除の対象になりえます。
しかし、海外子会社益金不算入制度を使用する場合には、その益金不算入配当に係る外国源泉税は損金算入もできませんし、外国税額控除の適用もできないことになっています。
これは、外国税額控除は国際的な二重課税の防止を目的とする制度であり、海外子会社配当の益金不算入で既に二重課税は排除されているので、外国税額控除まで認める必要はないという趣旨です。
なお、複雑なのが、上記ポイントで解説した現地で損金算入される配当についてです。日本の海外子会社益金不算入制度を使用しなかった部分については、外国源泉税について損金算入もしくは外国税額控除を適用することができます。現地で損金算入される配当がある場合の配当と外国源泉税等の取り扱いについて、以下の表にまとめました。
 きし
きし実額法で損金算入配当に対応する部分の外国源泉税については、外国税額控除を適用できる可能性があるので、検討漏れのないようにしましょう。
表:現地で損金算入される配当がある場合の配当と外国源泉税等の取り扱い
| 処理方法 | 配当の取り扱い | 外国源泉税等の取り扱い |
|---|---|---|
| 原則法 | 益金算入 | 損金算入 or 損金不算入+外国税額控除 |
| 実額法 | 【損金算入配当に対応する部分】 益金算入 | |
| 【損金算入配当に対応する部分以外のうち95%相当額】 益金不算入 | 損金不算入+外国税額控除不可 | |
| 【損金算入配当に対応する部分以外のうち5%相当額】 益金算入 |
タックスヘイブン対策税制と併用する場合の処理方法|合算課税との関係
ここからは応用編になります。配当を支払う海外子会社が、タックスヘイブン対策税制の適用対象になるような場合には、上記とは別の取り扱いが設けられています。
タックスヘイブン対策税制の適用対象となると、海外子会社の所得を日本の親法人の所得に合算するかたちになります。そうすると、タックスヘイブン対策税制の適用対象の海外子会社から配当を受け取った場合に、その配当にも課税をしてしまうと、タックスヘイブン対策税制の合算課税と二重課税になってしまいます。
この二重課税を排除するために、上記の95%相当額の益金不算入とは別に、合算課税済みの金額までは5%すら引かずにその満額を課税対象外とする取り扱いが設けられています。
なお、この取り扱いは、株式等の保有割合が25%未満など、上記の外国子会社益金不算入制度の適用要件を満たしていなくても適用できます。 これを踏まえ、以下の2パターンの場合の配当と外国源泉税等の取り扱いを見ていきます。
パターン①:タックスヘイブン対策税制の合算課税有り+外国子会社益金不算入制度の適用有り
このパターンの場合の配当と外国源泉税等の取り扱いは以下の通りです。
| 配当の取り扱い | 外国源泉税等の取り扱い |
|---|---|
| 【合算課税済に対応する配当】 益金不算入 | 損金算入 |
| 【合算課税済を超える部分に対応する配当×95%】 益金不算入 | 損金不算入+外国税額控除不可 |
| 【合算課税済を超える部分に対応する配当×5%】 益金算入 |
合算課税済みに対応する配当と、それ以外の部分で分けて考えると分かりやすいと思います。
パターン②:タックスヘイブン対策税制の合算課税有り+外国子会社益金不算入制度の適用無し
このパターンの場合の配当と外国源泉税等の取り扱いは以下の通りです。
| 配当の取り扱い | 外国源泉税等の取り扱い |
|---|---|
| 【合算課税済に対応する配当】 益金不算入 | 損金算入 |
| 【合算課税済を超える部分に対応する配当】 益金算入 | 損金算入 or 損金不算入+外国税額控除 |
外国子会社配当の会計処理|税効果会計と税率差異注記の実務ポイント
外国子会社益金不算入制度については、会計処理上の留意点もいくつかあるので以下で解説いたします。
税率差異注記での開示方法|受取配当金の永久差異に注意
日本親会社においては、海外子会社からの配当は受取配当金として収益計上されますが、税務上は外国子会社益金不算入制度を適用すれば法人税等の課税はありません。
そのため、会計上の利益と税務上の利益(課税所得)の差異要因になります。さらに、これは将来どこかで解消されるような差異(一時差異)ではなく、いわゆる永久差異と呼ばれる項目であるため、税率差異の注記の記載要因となります。項目名としては「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」として開示されることが多いかと思います。
なお、連結財務諸表上は、個別財務諸表上の受取配当金は子会社の支払配当金と相殺消去されるため、税率差異の要因にはなりません。
 きし
きし連結税率差異注記を作成する際に、受取配当金の益金不算入の項目が残ってしまわないように注意しましょう。
繰延税金資産の回収可能性|課税所得見積時の益金不算入調整
繰延税金資産の回収可能性を検討する際に、将来の課税所得を見積もります。
この課税所得の見積にあたっては、事業計画等の損益計算書の数値をベースにすることが多いかと思います。その際に、損益計算書の数値に海外子会社からの受取配当金が加味されている場合は、課税所得の見積の際には益金不算入の調整を忘れないようにしましょう。
連結財務諸表での税効果会計|内部留保に係る繰延税金負債の計上
連結財務諸表上、海外子会社の内部留保金額に対しては、個別財務諸表と連結財務諸表の海外子会社の簿価の相違要因になるとして、繰延税金負債を計上することになっています。
この点、海外子会社の内部留保のうち、日本親会社へ配当が見込まれる金額に関しては、その配当によって見込まれる追加の税負担金額を繰延税金負債として計上します。
海外子会社益金不算入制度を適用する場合に、海外子会社から日本親会社へ配当を送金するにあたって追加で発生する税負担額は、「配当等の額×5%×日本親会社の実効税率」+「海外現地で納付する源泉所得税」になりますので、両者の金額を見積もって、連結上の繰延税金負債として計上します。
まとめ
外国子会社益金不算入制度の概要や要件、さらに会計処理上の留意点について解説いたしました。
適用要件を満たすことができれば、海外子会社からの配当をほとんど無税にできる素晴らしい節税制度です。
ただし、要件にはいくつか注意点もありますので、適用漏れのないよう、十分な検討が必要です。また、外国税額控除やタックスヘイブン対策税制などの他の国際税務の論点も絡んでくるため、最終的には国際税務に強い税理士に相談することをおすすめいたします。
お気軽にお問い合わせください
マロニエ会計事務所では、「外国子会社配当益金不算入制度」をはじめとする国際税務に関するご相談を積極的にお受けしております。貴社の状況に応じ、以下のような支援が可能です。
- 外国子会社配当益金不算入制度の適用判定
株式保有割合や保有期間の要件を確認し、制度適用の可否を判断します。租税条約による保有割合緩和の検討も行います。 - 配当スキームの税務設計
海外子会社からの配当について、最も税負担が少なくなる送金方法や時期をご提案します。 - 外国源泉税と外国税額控除の最適化
現地で損金算入される配当がある場合の原則法・実額法の選択や、外国税額控除との併用を検討します。 - タックスヘイブン対策税制との併用対応
合算課税対象となる海外子会社からの配当について、二重課税を避けるための適切な処理をサポートします。 - 税効果会計と開示対応
税率差異注記、繰延税金資産の回収可能性判断、連結財務諸表での税効果会計など、会計処理全般を支援します。
貴社の海外子会社の所在地や事業内容、配当方針に合わせ、最適な税務対応策をご提案します。
 きし
きし「海外子会社から配当を受け取る予定だが税金が心配」「保有割合が25%未満だが制度を使えないか」「タックスヘイブン税制と併用する場合の処理方法を知りたい」「税効果会計の処理が正しいか確認したい」といった具体的なご相談はもちろん、「これから海外進出を検討しているが税務上の影響が知りたい」といった初期段階のご相談も歓迎しております。
初回のご相談やお見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
\ 24時間受付しております!/