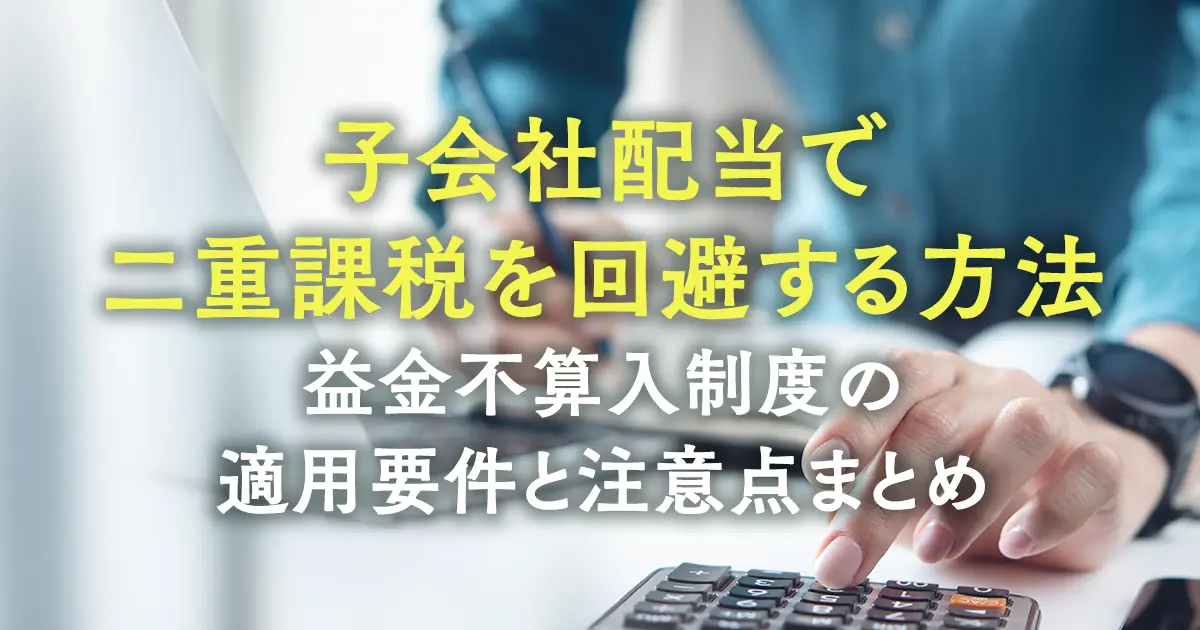きし
きしこんにちは。法人税務・グループ再編に強い、栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。
子会社が利益を上げ、現預金などの資産が積みあがって来た場合、投資の回収として親会社が現預金や不動産などの現物資産の配当を受けることはよくあると思います。
配当の原資に関しては、一度子会社で法人税が課税されていますので、親会社が配当を受けた際にも課税してしまうと二重課税になってしまうことから、一定の要件を満たす場合には親会社が受ける配当の一定額については法人税が課税されない益金不算入制度があります。
しかし、益金不算入制度を利用するにあたっては、複雑な要件があり、かつ、配当を行う資産が金銭か現物かどうかでも適用される制度が変わってきます。
なお、本記事は令和7年4月1日時点の法令等に基づいて記載しております。
子会社配当の税務処理は「金銭配当」と「現物配当」で大きく異なる
配当について、税務上は大きく2つの区分になっています。
金銭を配当する「金銭配当」と、金銭以外の現物資産を配当する「現物配当(分配)」です。
金銭を配当するか、現物資産を配当するか、で適用される税制が大きく変わってくるため注意が必要です。 子会社から配当で投資を回収する際には、適用される税制も踏まえて、回収する資産の種類を検討する必要があります。
金銭配当の益金不算入制度|保有割合別の税務処理と源泉徴収の要否
金銭配当を行う場合に検討すべき項目は、「その配当に課税が行われるか?」(株主側の観点)と「配当支払時に所得税の源泉徴収を行うか?」(支払側の観点)です。
株主側の課税に関しては、内国法人から受け取る配当に関しては、株式等の保有割合によって、配当のうち一定額が益金不算入となります。
これは、配当の原資は配当を支払う法人の側で一度法人税が課税されており、配当の受け取り時点でまた法人税を課税してしまうと二重課税になってしまうためです。
 きし
きしただし、保有割合の少ない投資目的の株式の配当については、益金不算入の割合が低めに抑えられています。
また、配当支払いの際の源泉徴収に関しても、株式等の保有割合によって、源泉徴収要否が変わってきます。
保有割合による4つの区分と税務処理
保有割合による4つの区分と税務処理を一覧表にまとめると以下の通りです。
内国法人から配当を受ける場合の課税の取り扱い:*5,*6
| 区分 | 株式等の保有割合 | 受取配当等の益金不算入額 | 源泉徴収 |
|---|---|---|---|
| 完全子法人株式等*1 | 100%*2 | 配当等の額×100% | 不要 |
| 関連法人株式等*1 | 3分の1超100%未満*2 | 配当等の額×100%-負債利子の額*3 | 不要*4 |
| その他の株式等 | 5%超3分の1以下 | 配当等の額×50% | 必要 |
| 非支配目的株式等*1 | 5%以下 | 配当等の額×20% | 必要 |
*1完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて保有割合を判定します。
*2配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して株式等を保有することが求められます。なお、計算期間とは、前回の配当等の額の基準日の翌日からその配当等の額の基準日までの期間をいいます。また、この保有期間の要件を満たさない場合には「その他の株式等」の区分による益金不算入割合が適用されます。
*3関連法人株式等の配当等の額の4%相当額(ただし、当該法人が借入金等の利子を実際に支払っているときは、その支払利子等の額の10%を上限)となります。
*4源泉徴収の要否の判断においては、保有期間の要件はありません。したがって、株式等の保有割合が3分の1超100%未満の配当に関しては、益金不算入割合は50%(その他の株式等)だが、源泉徴収は不要というケースが発生し得ます。
*5外国法人からの配当に関しては適用がありません。ただし、一定の要件を満たす海外子会社からの配当に関しては別途益金不算入制度が用意されています。
*6自己株式取得や残余財産分配時に発生する税務上のみなし配当も益金不算入制度の対象になります。
M&A後の配当実行で注意すべき保有期間要件
特筆すべき注意点として、完全子法人株式等、関連法人株式等における保有期間の要件です。
ただし、すぐに子会社から資金を回収しなければならないようなケースもあると思います。
その場合には、1度期中で臨時配当を行って配当の計算期間をリセットして、再度配当を実施するという方法も考えられます。ただし、益金不算入を適用するための形式的な配当であるとして臨時配当が税務調査で否定される可能性もありますので注意してください。
また、「その他の株式等」と「非支配株式等」の株式等の保有割合の要件を逆に理解してしまっている事例も多く見受けます。株式等の保有割合が5%以下であるのに、なぜか「その他の株式等」として益金不算入割合を判定してしまっているのをよく見かけます。
 きし
きし思い込みを捨て、各区分の要件に当てはめて判定を行うようにしましょう。
現物配当(現物分配)の税務処理|適格・非適格の判定要件と課税関係
金銭ではなく株式や不動産などの現物を配当する場合には、税務上は金銭配当とは異なる制度が適用されます。税務上は「現物分配」といったりします。
現物分配は組織再編税制の中で整理されており、適格現物分配か非適格現物分配か、で税務処理が変わってきます。
適格/非適格現物分配の要件や被現物分配法人(分配を受ける法人)と分配法人(分配を行う法人)の税務処理は以下の通りです。
現物分配の課税関係
| 区分 | 要件 | 被現物分配法人側の処理 | 分配法人側の処理 |
|---|---|---|---|
| 適格現物分配 | 現物分配法人及び被現物分配法人が、いずれも内国法人であること。 現物分配により資産の移転を受ける者が、現物分配の直前において現物分配法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであること。 | 分配資産を簿価で受入れ 分配による利益は全額益金不算入 分配前の繰越欠損金や保有資産の含み損について、一定の場合に使用が制限される | 分配資産の含み損益は実現しない 源泉徴収不要 |
| 非適格現物分配 | 適格現物分配に該当しない場合の現物分配 | 分配資産を時価で受入れ 分配による利益は全額益金算入 | 分配資産の含み損益が実現 源泉徴収必要 |
直感的に分かりづらく、また制度的な批判もあるのですが、配当を金銭以外の資産で行う「現物分配」に関してはなぜか組織再編税制として整理されてしまいます。
この結果として、適格現物分配において、被現物分配法人の適格現物分配の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続して支配関係があること等の要件を満たさない場合には、合併等の組織再編税制と同様に、被現物分配法人の繰越欠損金の使用が制限されるといったような規制が働きます。
一方で現物分配に関しては非常に使いやすい面もあり、適格現物分配の判定にあたっては、完全子法人株式等の配当のように株式等の保有期間の制限がありません。現物分配の直前に完全支配関係があれば良いのです。
そのため、被現物分配法人の繰越欠損金や分配資産の含み損などを考慮しなくてよい状況ならば、M&A等で株式を取得した後すぐに、不動産や株式などを親会社に無税で移転することができます。
また、現物分配は、会社法上は単なる配当なので、合併や会社分割のような債権者保護手続き等の面倒な手続きが不要です。
また、分配資産を譲渡により親会社に移転する場合と比べると、分配は配当なので消費税が課税されないというのもメリットです。
金銭配当vs現物分配|メリット・デメリットと使い分けのポイント
配当の対象が金銭か現物というそもそもの部分が異なりますので一概に比較をすることは難しいです。
適格現物分配の方が保有期間要件がなく税務上使いやすいからという理由で現物分配を行おうとしても、不動産や株式などの現物は流動性も低く、登記などの手続きも必要になってきてしまい、手間がかかるケースもありますからね。
しかし、両制度に言えることは、使いこなせば非常に強力な節税策になるということです。
完全子法人株式等の配当を使用すればグループ内の資金移転を無税で実行可能ですし、適格現物分配は有効活用すれば孫会社株式を子会社から無税で配当してグループ内の再編にも利用できます。
子会社から金銭や現物を配当する際に、配当する対象によって適用される税制が異なるという点は理解しておき、配当の目的に応じて両制度をうまく使い分けていただければよいかと思います。
子会社簿価減額特例(ソフトバンク税制)|配当後の株式譲渡で注意すべき規制
配当の副次的な効果ですが、配当を行った法人の純資産が配当資産分だけ減少しますので、配当を行った法人の税務上の株価を下げることができます。
これを悪用して、無税の配当で子会社から資金を吸い上げ税務上の株価の時価を引き下げ、当該引き下げ後の時価で子会社の株式を譲渡し、多額の譲渡損を計上して法人税の節税を行うといったことが可能でした。
しかし、このような節税スキームを防止するために、2020年度税制改正で「子会社簿価減額特例」という制度が創設されました。
 きし
きしこの特例は、制度創設のきっかけとなった会社であるソフトバンクの名を取り、ソフトバンク税制とも呼ばれていたりします。
ソフトバンクは、上記の無税配当による時価引き下げとその後の譲渡(現物出資)によるスキームにより1~2兆円程度の譲渡損を作り出したと言われており、それに国税庁がお怒りになりこの制度ができました。
子会社簿価減額特例の創設により、完全子法人株式等の配当、適格現物分配、外国子会社配当等を受ける場合には、その益金不算入の配当額のうち一定額を子会社株式の簿価から減額する調整を行うこととなりました。
これにより、税務上の株価の時価が下がった分、税務上の子会社株式の簿価も減少するため、株式を譲渡した際に配当で吸い上げた部分の金額の譲渡損は計上されないかたちになります。
なお、詳細は割愛しますが、一定の要件を満たす場合には子会社簿価減額特例の適用対象外となるケースもあります。
子会社配当の益金不算入制度を活用する際の重要ポイント
子会社から配当を受ける際の益金不算入制度について、要件や注意ポイントを解説してきました。益金不算入制度は有効活用できればグループ間の資産移動を無税で実行できる反面、要件を1つでも満たしていないと多額の課税が生じてしまいます。
配当の実行にあたっては、事前に専門家である税理士に相談し、節税効果の高い最適な配当戦略を計画する必要があります。
お気軽にお問い合わせください
マロニエ会計事務所では、「子会社配当の税務・益金不算入制度」に関するご相談を積極的にお受けしております。貴社の状況に応じ、以下のような支援が可能です。
- 益金不算入制度の適用可否判定
株式保有割合や保有期間要件を精査し、最適な配当実行タイミングをご提案します。 - 金銭配当と現物分配の選択支援
配当する資産の種類に応じて、税務上最も有利な方法を検討・提案いたします。 - M&A後の配当戦略立案
株式取得後の配当実行における保有期間要件や適格要件を考慮した最適なスキームを設計します。 - 適格現物分配の要件確認と手続き支援
完全支配関係の確認から繰越欠損金の制限まで、適格現物分配の要件を総合的に検討します。 - 子会社簿価減額特例への対応
配当後の株式譲渡時における簿価減額の影響を事前に計算し、適切な対策を講じます。
貴社のグループ構造や資金需要に合わせ、最適な配当戦略をご提案します。
 きし
きし「子会社から無税で資金を回収したい」「現物分配で不動産を親会社に移したい」「M&A後すぐに配当を実行したいが税務リスクが心配」といった具体的なご相談はもちろん、「グループ内資金の効率化を図りたい」「配当による節税効果を知りたい」といった初期段階のご相談も歓迎しております。
初回のご相談やお見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
\ 24時間受付しております!/