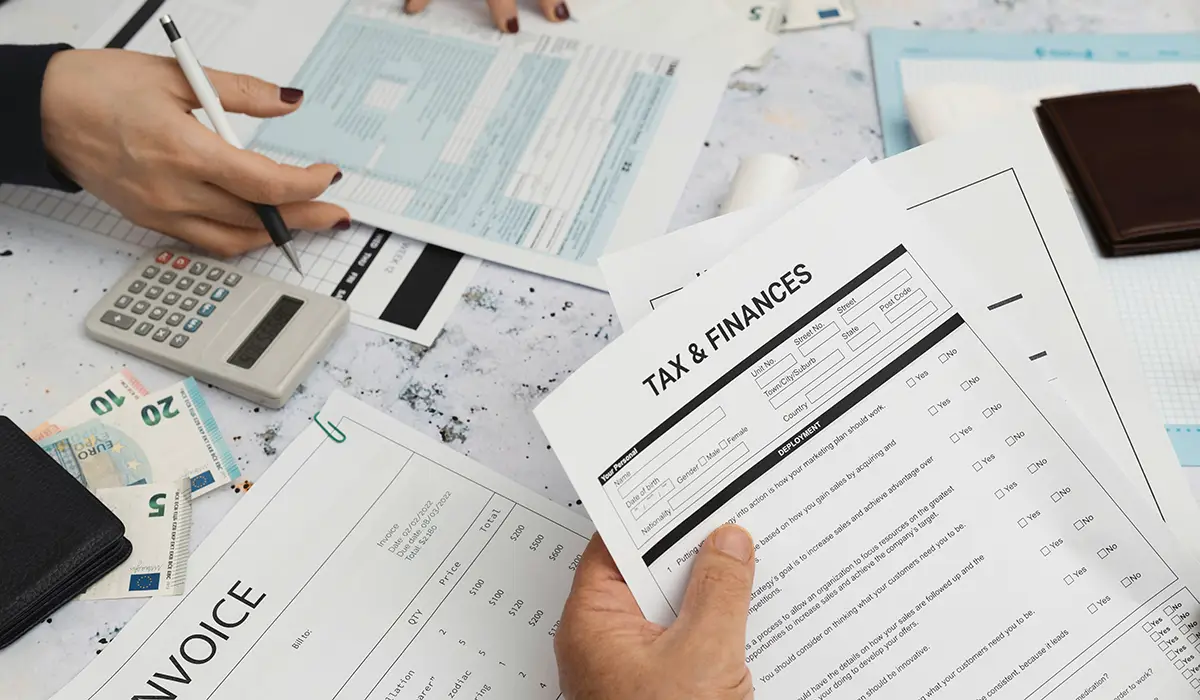きし
きしこんにちは。正しい節税をおすすめする栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。
「税金を減らすために毎期利益を出さないようにして節税しているのに、なぜ会社にお金が残らないのだろう」と疑問に思っている経営者さんは多いのではないでしょうか。
冷静に考えれば、利益が出ていないのにお金が残るはずはないのですが、世の中には節税に対する誤った認識が根付いてしまっており、「節税をすればお金が増える」と誤解されている方が非常に多いと感じています。
もちろん、お金が増える節税もあるのですが、世の中で言われている節税策のほとんどは、税金は減りますが、それ以上にお金が減ってしまうものが大半です。
そこで今回は、節税とお金の関係について、解説していきます。
節税額よりキャッシュアウトが大?節税と資金繰りの関係を事例で解説

早速ですが、具体的な数値に基づいて節税とお金の動きの関係性を見ていきたいと思います。
このような場合、ベンツを購入した場合と、購入しなかった場合の税金とお金の動きは以下のようになります。
事例:中古ベンツ購入による節税効果と残る資金の比較
※ベンツは1年で全額、減価償却費が計上できると仮定します。
※法人税率は30%と仮定します。
法人税:(利益500万円 ― ベンツ400万円)×30%=30万円
支出額:ベンツ△400万円
残る資金:利益500万円―法人税30万円―ベンツ400万円=70万円
※法人税率は30%と仮定します。
法人税:利益500万円×30%=150万円
支出額:0円
残る資金:利益500万円―法人税150万円=350万円
ベンツを購入した場合と、購入しなかった場合とでは、残る資金に280万円もの差が生じてきます。
これが、ちょうど車の買い替えの時期であったというような場合には、いずれにせよ支出するお金だったので、この280万円の差が全て損になるということではありません。
しかし、節税のためだけに無理して購入したベンツであったならば、たしかに法人税は減りますが、それ以上に会社に残るお金が減る結果になるのです。
何かしらの資金の支出を伴う節税策に関しては、総じて同様のことが言えます。節税だけに目が行ってしまうと、会社のお金を減らす結果になってしまうのです。
要注意!会社のお金を減らす「危険な節税策」と賢い節税策
世の中にはたくさんの節税策がありますが、そのほとんどは結果として会社のお金が減ってしまう節税策です。一方で、中には、資金の支出を伴わず、会社のお金を減らすことのない節税策もあります。
以下、メジャーな節税策ごとに解説していきます。
キャッシュが流出する?見直すべき7つの「お金が減る節税策」

一見すると税金が減ってお得に思える節税策の中には、支払う税金以上に会社のキャッシュを減らしてしまうものも少なくありません。ここでは注意すべき代表的な7つのケースを見ていきましょう。
① 不要不急?車・消耗品の購入による節税の落とし穴
これらは、車や消耗品の購入にあたってお金を支払うので、結果として会社のお金が減る節税です。
ちょうど購入のタイミングであったならば、会社のお金が減ってもそれは適切な投資の結果なので問題はないかと思いますが、節税のためだけに車や消耗品を購入することは資金繰りの観点からは避けた方が良いかと思います。
② 法人保険での節税は本当?繰延効果とデメリット
これも、結果として会社のお金が減るケースがほとんどです。
保険の営業さんが、節税を売り文句として保険を勧めるケースがあります。
このように、結局将来のどこかで課税され、単に課税を繰り延べているに過ぎない節税策を、繰延型の節税策と言ったりします。
また、本記事執筆日現在の税法では、解約返戻金が相当額戻ってくる保険は最大でも保険料の4割しか経費にできません。
 きし
きしさらに、4割を経費に落とすための保険は仕組み上、ピークの解約返戻率が100%に達することはなく、元本割れしてお金が戻ってくることになります。
これらのことから、現状、法人税の節税目的で保険に加入するメリットはほとんどないと考えています。保険の営業さんが節税策として保険を勧めてきたら注意しましょう。
一方で、社長が死亡した際などの保障目的として保険に加入することは大賛成です。
保険は節税ではなく、保障の観点で選ぶようにしましょう。
③ 倒産防止共済(セーフティ共済)は節税か?将来の課税リスク
これも、結果として会社のお金が減る節税です。倒産防止共済は掛金の支払い時にその掛金の全額が経費になります。年間最大で240万円まで掛金を支払うことが可能です。
そして、一定期間加入し続ければ、必ず掛金累計額の100%が解約金として返ってきます。
しかし、解約金が返ってくる時点で、その全額が雑収入として課税されますので、保険と同様に繰延型の節税策です。
④ 役員報酬・賞与の増額は最適?社会保険料と資金繰りへの影響
これも、結果として会社のお金が減る節税です。利益が出そうになると、役員報酬や役員賞与の金額を、赤字スレスレの水準まで増額させる方をよく見受けます。
中小企業の場合は、会社と役員は一心同体のような会社がほとんどですので、会社からお金がなくなっても、役員個人でそのお金を残していれば、法人+個人全体としてお金は減っていないとも考えられるかもしれません。
しかし、役員報酬や賞与には社会保険料が課税されますので、その分は法人+個人の外部にお金が流出します。
また、個人に入ってきたお金をそのまま浪費してしまえば、結局は法人からお金が減っているだけになってしまいます。
将来設備投資や人員増加、銀行融資を考えておらず、1人、2人の社員で会社を運営していく場合には、会社に多くのお金を残す必要はないかもしれません。
 きし
きし会社の経営方針と整合した節税策を採用することが重要です。
⑤ オペレーティングリースはハイリスク?節税効果と注意点

これは、結果としてお金が増えるケースもあれば、減るケースもある節税です。
多額の利益が生じている会社さんは、銀行などから航空機やコンテナに出資するオペレーティングリース商品の購入を勧められるケースがあるかと思います。
これは、出資した金額の大半が出資した期の損金になり、将来、出資金の分配があった際に収益として課税される繰延型の節税策になります。
為替が円安に振れたり、リース物件の収支が想定を上回れば、出資よりも多くのお金が戻ってくることもありますが、リース先の会社が潰れて出資額が一切戻ってこないケースもあります。
また、出資金の分配も、商品購入時にある程度の計画は立てられていますが、実際には分配の時期がズレる可能性もあります。
⑥ 家賃前払いは有効な節税?短期的な効果と継続の難しさ
これは、短期的に会社のお金を減らす節税策です。
利益が出そうになると、決算月に向こう1年の家賃を前払いする方もいるかと思います。
短期前払費用は支払時の経費になりますので、法人税はたしかに減ります。
将来の資金繰りも悪化させてしまいます。
 きし
きし会社の資金繰りとの関係で見ると、あまりおすすめはできない節税策です。
⑦ 出張旅費日当は節税になる?法人と個人の資金管理
これは、結果として会社のお金が減る節税策です。
出張旅費規程を整備して、役員や従業員に旅費日当を支払うケースがあると思います。
旅費日当に関しては、社会通念上妥当な範囲の金額であれば、旅費交通費として法人の経費になり、受け取った個人の側も所得税が課税されないので、メジャーな節税策の1つです。
しかし、これも④の役員報酬の増額と同様で、会社から個人にお金が流出してしまいますので、個人で受け取ったお金を浪費してしまったりすると、法人+個人の合計で見た場合のお金が減ってしまい、会社の資金繰りを圧迫してしまいます。
追加コストなし!キャッシュを守る・増やす「お金が減らない節税策」4選
一方で、追加の資金支出を伴わずに税負担を軽減できる、あるいは結果的にキャッシュを守ることにつながる節税策も存在します。活用できる制度や方法がないか確認しましょう。
① 税額控除(賃上げ・投資促進税制)を活用して賢く節税
これは、追加の資金支出がなく、会社のお金を増やす節税策です。
前期よりも従業員の賃金を増加させた場合に適用できる税額控除や、特定の設備を購入した場合の税額控除制度を適用できれば、追加の資金支出がなく、会社の税負担を減らすことができます。
適用漏れのないように、適用要件や必要書類を確認しておきましょう。
② 眠っていませんか?不良在庫の廃棄による損失計上

これは、追加の資金支出がなく、会社のお金を増やす節税策です。
 きし
きし過去に購入や製造をしたのは良いが、売れ残ってしまい、そのまま棚に残っている在庫はないでしょうか。
棚卸資産の中に不良在庫がないかは是非チェックしておきたいところです。
③ 回収不能な売掛金は?不良債権の貸倒処理で税金を取り戻す
これは、追加の資金支出がなく、会社のお金を増やす節税策です。
請求したは良いが、相手先からの入金がない売掛金や未収金はないでしょうか。これらは、計上時に売上を計上しているため、その時に法人税や消費税を支払っていますが、対応するお金が入金されていないので、税金だけを支払っているという非常に損をしている状態になっています。
税務上の貸倒損失計上の要件は複雑ですが、要件を確認して貸倒処理することができれば、売上計上時に納めていた税金を回収することができます。
④ 法人税率の差を利用した繰延型節税の活用タイミング
これは、主に繰延型の節税策を活用した節税です。
基本的に保険や倒産防止共済などの繰延型の節税策は、トータルの期間で見ると節税にはならないケースが多いことを解説いたしました。
一方で、中小企業の法人税率は、課税所得800万円を境に、15%から23.2%に上昇します。
そのため、たまたま土地の売却や高利益の受注が発生して800万円超の利益が出てしまう期に、繰延型の節税策で一旦課税される収益を将来に繰り延べれば、法人税の税率を下げることが可能になります。
「節税のやりすぎ」が招く悲劇:資金繰り悪化と融資不可の事例紹介

では、お金が減る節税策を続けた会社はどのような結末が待ち受けているのでしょうか。以下で実例を解説いたします。
事例1:過度な役員報酬で資金ショート寸前になったA社
A社は従業員を5~6名程度抱える製造業です。社長は法人税の支払いを避ける目的で、いつも会社の利益が赤字もしくは赤字スレスレの水準になるように役員報酬を増額し続けていました。
そして、役員報酬として受け取った金額は自分個人のお金と考え、自宅の購入や子どもの学費にほとんど使っていました。
そのような経営を何年も続けており、たしかに法人税の支払いは毎期ほとんどないのですが、会社の預金口座にはお金がなかなか残らず、毎月の仕入先への支払いを払うのがやっと、という状況でした。
そのため、新規の設備を購入したくてもお金がないといった状況でした。
その結果、設備も陳腐化し、取引先からの受注が徐々に減少し、売上は最盛期の半分程度になってしまいました。
事例2:赤字決算続きで銀行融資を断られたB社
B社は従業員を10名程度抱える建設業です。社長は法人税で持っていかれるくらいなら経費としてお金を使ってしまおうと考えている方でした。
利益が出そうになると、不要不急の車や重機の購入、役員報酬の増額などを続けていました。その結果、損益計算書の利益は毎期ほとんど発生せず、貸借対照表の純資産はマイナスでした。
そして、徐々に会社の資金繰りが悪化してしまい、銀行に追加の融資を申請したのですが、融資を断られてしまいました。銀行は損益計算書や貸借対照表を見て、その会社に資金の返済能力があるかどうかを審査します。
納税への意識改革がカギ!会社の資金繰りを根本から改善する思考法
会社の資金繰りを良くするための考え方として重要な点は、「納税に対する嫌悪感、苦手意識をなくす」といった点に尽きるかと思っています。
節税はもちろん経営にとって重要な要素です。活用できる節税策は積極的に活用すべきです。
 きし
きし筆者自身も事業の利益に対して納税を行うのですが、税理士である自分ですら「法人税って高いな」、「消費税ってもっと安くならないのかな」と思ったりしています。笑
しかし、税金を支払わないと会社にお金が残らない仕組みになっているということを理解していますので、無理な節税策を行うようなことはなく、素直に納税を行って、会社にお金を残すようにしています。
残念ながら世の中の経営者さんの多くは、この「税金を支払ってお金を残す」という仕組みを理解していないように感じます。
そのため、経営者仲間からも、「法人税を払うくらいなら中古の高級車でも買いなよ」とか、「役員賞与をいっぱい出して節税しなよ」と言われるようなことが多いと思います。
しかし、その周りの言葉を押し切って、勇気をもって利益を出して納税し続ければ、会社にお金が残る好循環が生まれ、会社が成長していきます。
そうすれば、余裕資金で設備投資や人材採用を行うことができ、競合他社を上回る会社を作ることができます。
 きし
きし勇気をもって納税して、会社の資金繰りを良くしましょう!
まとめ:節税と資金繰りの最適バランスを見つけ、成長する会社へ

節税策とお金の関係性や、節税に対する考え方などを解説いたしました。
税金だけはなく会社全体のお金の動きを見渡して、結果として得をしているのか損をしているのかを、他人や世間一般の声に惑わされずに判断してみてください。
そうすると、納税に対する嫌悪感もなくなり、「税金を支払ってお金を残す」を実践することができ、会社の資金繰りも良くなっていくかと思います。
お気軽にお問い合わせください
マロニエ会計事務所では、「法人の節税と資金繰り改善」に関するご相談を幅広くお受けしております。たとえば、以下のような支援が可能です。
- 貴社の節税策の診断と見直し: 現在実施されている節税策が、キャッシュフローにどのような影響を与えているかを分析し、最適な節税戦略をご提案します。
- 資金繰りを圧迫しない節税策の提案・実行支援: 税額控除の活用、不良在庫や不良債権の適切な処理、法人税率差の活用など、キャッシュを守りながら税負担を最適化する方法をご支援します。
- キャッシュフロー改善コンサルティング: 節税だけでなく、会社全体のお金の流れを把握し、キャッシュフローを安定・改善させるための具体的な計画立案と実行をお手伝いします。
- 健全な決算対策と納税計画の立案: 無理な節税に頼ることなく、会社の成長につながる適切な利益確保と納税計画をご提案します。
- 銀行融資に強い財務体質づくり: 金融機関から評価される決算書作成のアドバイスや、将来の融資を見据えた事業計画策定をサポートします。
- 役員報酬・賞与の最適化シミュレーション: 会社の資金状況と経営者個人のライフプランを考慮し、社会保険料負担等も踏まえた最適な役員報酬・賞与のバランス設定を支援します。
こうした幅広い支援メニューを取りそろえ、貴社の現状や経営方針、将来の展望に合わせた柔軟な対応をいたします。
 きし
きし「節税しているはずなのにお金が残らない」「どの節税方法が自社にとって本当に有利なのか分からない」「目先の税金だけでなく、将来のために会社にお金を残したい」「資金繰りを安定させたい」など、まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。
初回のご相談やお見積もりも無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
\ 24時間受付しております!/